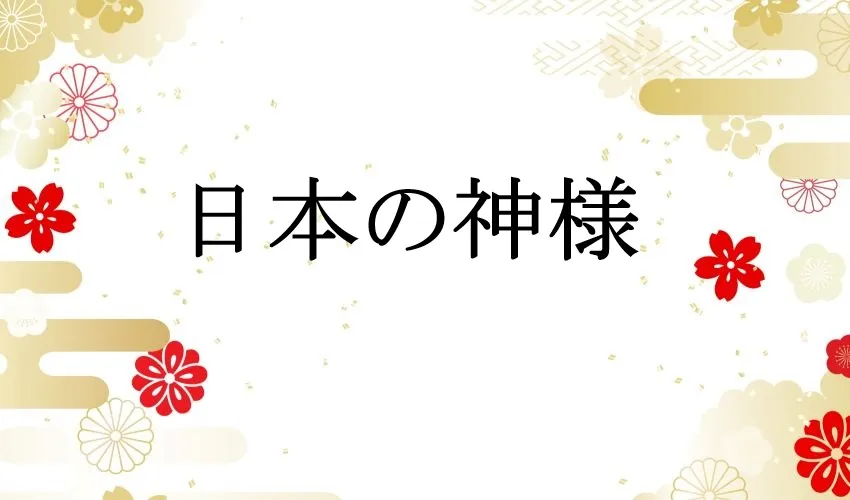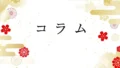日本の神様とは、どんな存在なのでしょうか?
日本の神様は多種多様で定義や分類が難しいとされています。専門に研究している学者であっても、これぞという決定的な定義や分類を提示できずにいます、なぜなのでしょうか?
この記事では、日本の神様は定義づけが難しい理由、難しいもののある程度の分類ができること、分類することの意義、分類・種類ごとの神様の一覧を紹介しています。
日本の神様に関しては、神様の一覧に関するネット検索が非常に多いことから、まず、神様の一覧から紹介します。
日本の神様の一覧

左から須佐之男命、天照大御神、月読命
日本の神様には、「古事記」「日本書記」(記紀という)に登場する天津神(あまつかみ)、国津神(くにつかみ)、人代神(じんだいしん)と、記紀に登場しない神様などに分類することができます。
代表的な神様を分類化して一覧にまとめてみました。各分類の詳細については、一覧の後で解説します。
分類別の神様の一覧
| 区分 | 分類 | 神様の名前 |
|---|---|---|
| 記紀に登場する神様 | 天津神 | 伊邪那岐命、伊邪那美命、、、、、月読命、天照大御神、須佐之男命、建御雷神、経津主神、邇邇芸命、天宇受売命 など |
| 国津神 | 大国主神、少名毘古那神、大物主神、建御名方神、事代主神、木花之佐久夜毘売命、石長比売命、櫛名田比売 など | |
| 人代の神 | 神武天皇、邇邇芸命日命、吉備津彦命、彦佐建命、日本武尊、神功皇后、武内宿禰命 など | |
| 記紀に登場しない神様 | 健磐龍命、八幡神、稲荷神 など | |
| 人神 | 菅原道真公、平将門公、崇徳上皇、御霊、安徳天皇、聖徳太子、小野篁公、安倍晴明公、藤原鎌足公、和気清麻呂公 など | |
| その他の神様 | 恵比寿神、道祖神、年神、荒神、竈の神、オシラサマ など | |
主な神様を祀っている神社一覧
代表的な神様を主祭神として祀っている神社を一覧化しました。
| 神名 | 主な役割・特徴 | 代表的な神社(主祭神) |
|---|---|---|
| 伊邪那岐命 | 天地創造・禊の神 | 多賀大社、伊弉諾神宮、淡路伊佐奈岐神社 |
| 伊邪那美命 | 創造神・死の神格 | 花の窟神社、伊邪那美神社、熊野本宮大社 |
| 月読命 | 月の神・夜の統治者 | 月読神社、月夜見宮、壱岐神社 |
| 天照大御神 | 太陽神・皇祖神 | 伊勢神宮(内宮)、高千穂神社、天岩戸神社、東京大神宮、芝大神宮 |
| 須佐之男命 | 海・嵐・祓いの神 | 須佐神社、八坂神社、氷川神社 |
| 建御雷神 | 武神・雷神 | 鹿島神宮、春日大社、武甕槌神社 |
| 経津主神 | 武神・国譲りの使者 | 香取神宮、春日大社、経津主神社 |
| 邇邇芸命 | 天孫降臨の主役 | 霧島神宮、鵜戸神宮、高千穂神社 |
| 天宇受売命 | 芸能・舞の神 | 佐太神社、天鈿女命神社、淡島神社 |
| 大国主命 | 国造り・縁結びの神 | 出雲大社、大国魂神社、大神神社 |
| 少名毘古那神 | 医療・酒造・国造りの補佐 | 少彦名神社、道修町神社、粟島神社 |
| 大物主神 | 蛇神・国土守護 | 大神神社、三輪神社、大物主神社 |
| 建御名方神 | 武神・諏訪の守護神 | 諏訪大社(上社・下社)、建御名方神社 |
| 事代主神 | 商業・釣りの神 | 美保神社、恵比寿神社、事代主神社 |
| 木花之佐久夜毘売命 | 火と出産の守護神 | 浅間神社、富士山本宮浅間大社、木花神社 |
| 石長比売命 | 長寿・岩の神 | 石長比売神社、木花神社(対比)、霧島神宮 |
| 櫛名田比売 | 須佐之男命の妻・農耕神 | 八重垣神社、櫛名田比売神社、須賀神社 |
| 神武天皇 | 初代天皇・現人神 | 橿原神宮、神武天皇陵、畝傍神社 |
| 邇邇芸命日命 | 天孫系の神(異表記) | 霧島神宮、鵜戸神宮、高千穂神社 |
| 吉備津彦命 | 桃太郎伝説のモデル | 吉備津神社、吉備津彦神社、吉備中山神社 |
| 彦佐建命 | 吉備地方の祖神 | 吉備津彦神社、彦佐建神社、備前一宮 |
| 日本武尊 | 東国遠征の勝利・武運の象徴 | 熱田神宮、大鳥神社、建部大社 |
| 神功皇后 | 三韓征伐の女傑 | 宇美八幡宮、香椎宮、住吉大社 |
| 武内宿禰命 | 忠臣・長寿の象徴 | 武内神社、住吉大社、香椎宮 |
| 健磐龍命 | 阿蘇の祖神 | 阿蘇神社、健磐龍神社、阿蘇郡の各社 |
| 八幡神 | 武神・応神天皇 | 宇佐神宮、鶴岡八幡宮、岩清水八幡宮 |
| 稲荷神 | 農業・商業の神 | 伏見稲荷大社、祐徳稲荷神社、豊川稲荷、笠間稲荷神社、豊川稲荷東京別院、東伏見稲荷神社 |
| 菅原道真公 | 学問の神 | 太宰府天満宮、北野天満宮、防府天満宮、湯島天満宮、谷保天満宮、亀戸天神社 |
| 平将門公 | 武勇・怨霊鎮め | 神田明神、筑波山神社、将門神社 |
| 崇徳天皇 | 怨霊・鎮魂の象徴 | 白峯神宮、崇徳天皇社、安井金刀比羅宮 |
|
御霊
|
怨霊鎮め・御霊信仰 | 上御霊神社、下御霊神社、御霊神社(全国) |
| 安徳天皇 | 壇ノ浦で崩御した幼帝 | 赤間神宮、安徳天皇陵、厳島神社(合祀) |
| 聖徳太子 | 文化・仏教の守護者 | 法隆寺、太子堂、橘寺 |
| 小野篁公 | 冥府往来の伝説 | 小野篁神社、六道珍皇寺、篁神社 |
| 安倍晴明公 | 陰陽師・占術の神 | 晴明神社(京都)、安倍晴明神社(大阪)、晴明神社(名古屋) |
| 藤原鎌足公 | 中臣鎌足・政治改革者 | 談山神社、鎌足神社、藤原神社 |
| 和気清麻呂公 | 忠臣・護国の象徴 | 護王神社、和気神社、清麻呂神社 |
日本の神様の定義が難しい理由
日本の神様には、ギリシャ神話に登場してくる神々のような人格神がいるかと思えば、動物の神、自然現象の神もいる。特定の日だけやってくる神様や、巨石や巨木、滝などに宿る神様もいる。
崇め奉られる神様だけでなく、忌み嫌われる神様や境界の外に追いやられる神様もいる。外国からやってきたという神様さえいる。
つまり、ものすごく多様性に富んでいるがゆえに、一言で定義しきれないのです。
江戸中期の国学者の本居宣長(もとおり のりなが)は、「人間の理解を超えた存在が神であり、それには善いこと、勇ましいこと、優れたことのほか悪しきことや怪しいことも含まれる」と「古事記伝」で述べています。
このような多様性によって明確な定義づけは難しいものの、そのことが日本の信仰の特徴となっており、日本の信仰に対する懐の広さ、つまり、信仰に対する「おおらかさ」に結びついていると言えます。
日本の神様のおおまかな分類
日本の神様は、あまりにも多種多様すぎて簡単に括ることはできず、また、完全に網羅することさえも難しいので定義付けは容易ではありません。
ですが、「おおらか」であるがゆえに、おおまかに分類することは可能で、おおまかに分類することで、それを知っておくだけでも、神社に祀られている神様たちの性質なども理解できるようになります。
では、どんな分類となるかというと、日本の神様は「古事記」「日本書記」、いわゆる「記紀」の神話に登場するか否かで、大きく2つに分類できるのです。
記紀神話に登場する神様が偉いというわけではないですが、朝廷などが記紀神話の神様を重視してきたことから、神社の本殿で祀られている神様は記紀神話の神様であることが多いのです。そのため、おおまかな分類であてっても、それを理解すれば神社で祀られている神様のことを理解しやすくなるわけです。
天津神、国津神、人代神の3つの分類が基本
「古事記」「日本書記」に登場する神様は、天津神、国津神、人代の神の3種に分類できます、まず、これらが分類の基本だといえます。
天津神(あまつかみ)
天津神は、高天原に住む天上の神々で、記紀神話の冒頭に登場します。
宇宙創成や秩序の維持を担い、天照大御神をはじめとする皇祖神が中心です。彼らは天孫降臨を通じて地上に関与し、天皇の祖先として国家神道の根幹を形成した神々です。
天津神は理念的・抽象的な性格を持ち、自然現象や宇宙原理を象徴する神が多く、政治的正統性の裏付けとしても機能しました。伊勢神宮や鹿島神宮など、国家的な祭祀の中心に位置づけられています。
国津神(くにつかみ)
国津神は、地上世界(葦原中国)に元々住んでいた神々で、自然・土地・民間信仰と深く結びついています。
出雲神話に登場する大国主命や須佐之男命が代表格で、農業・医療・海・山など生活に密着した領域を司ります。天津神と対比される存在であり、地域の土地神・氏神として各地に祀られています。
出雲大社や宇佐神宮などが信仰の中心で、民間信仰との融合も進んでいった神々です。国津神は「地に根ざした神々」として、地域文化や生活感覚に寄り添う神格です。
人代神(じんだいしん)
人代神は、神代(かみよ)から人代への移行期に登場する神々で、神話と歴史の境界に位置します。
人代とは、神々が地上を治めた神代の後、天孫降臨によって神の血を引く存在、つまり、現人神が地上に君臨し始める時代が「人代」とされます。
天孫降臨後に地上を治める邇邇芸命や神武天皇などが該当し、天皇の祖先として神格化されます。彼らは神性を持ちながらも人間的な活動を行い、政治的・文化的な統治者として描かれます。
記紀では天皇の正統性を示すために重要な役割を果たし、神話と現実の王権をつなぐ橋渡し的な存在です。神社では霊的存在として祀られることもあり、信仰と歴史の両面から尊崇されています。
記紀に登場しない神様、人神など
大きな分類の2つ目は、「古事記」「日本書記」に登場しない神様たちや人神(ひとがみ)などです。
記紀に登場しない神々
「古事記」「日本書記」に登場しない神々は、両書が編纂された当時、地域的な信仰に留まって大和朝廷とは関係を持たなかったため、記紀に収録されなかったものもあります。
そうした収録されなかった神様は「風土記」で語られていることが多く、八幡神や稲荷伸も記紀には記されていませんが、奈良時代以降に急速に信仰が広まり、現在ではもっとも有名な神様となっています。
人であった人神、民間信仰に由来する神々
もとは人間であったけれども、深い怨みを抱いて死んだ者や、並外れて大きな功績をあげた人が神様として祀られることもあり、そのような神様を人神(ひとがみ)といいます。たとえば、菅原道真公や平将門公などが人神に該当します。
さらに、恵比寿神や道祖神などの民間信仰に由来する神様もいたり、人とのかかわりの違いから「氏神(うじがみ)」「産土神(うぶすながみ)」「霊威神(れいいしん)」といった分類で呼ばれている神様もいます。
この記事のまとめ
ここまで読まれてみていかがでしたか。
日本の神様の世界は、想像以上に奥深く、そして自由です。定義しきれないほど多様でありながら、「おおまかに分類する」ことで、どんな神様が祀られていて、その神様が祀られている意味や背景も見えてくると思います。
天津神の天の秩序、国津神の地の豊穣、人代神の現人神としての統治、そして民間信仰や人神、それぞれが日本の信仰や文化を形づくっています。
今回紹介した日本の神様の一覧で、神々の分類を知ることは、単なる知識ではなく、神社参拝や文化体験をより豊かにする糧となるはずです。ぜひ、参考にして神社へ参拝してみてください、新たな発見があるかもしれません。